ず~~っと昔から考えては挫折しているのだが、やはり日記はつけるべきである。アラサーですらなくサーにもなるとその当時どんな思考してたか何を考えた末結局何をやって何をやらなかったかみたいな経緯がおぼろげになる。
同様の理由で写真なんかもなるべく残すようにしている。特に今エストニアにいる時代は自由度も高く記録する意義がありそうなものである。
が、毎日とか毎週はきついので、月単位ならギリギリ継続できる気がするので月刊誌とする。まあガチでなんもしてない月とかも出てきそう。
とりあえず今回は8月までをまとめて書く。原則前の博士報告の続きである。ほかの記事はわりと対外向けに書いてるがここはガンガン専門的な話を含む自分用になる。
研究
春夏は研究や実験自体はほとんど実質的な進捗はなかった。発表はしているものの、全て昨年秋頃に提出したもののみである。発表したら以前のリバイスが帰ってきて編集や追加実験など手戻り的なタスクの割合が多い。
バタバタしたり学会に行ってる割にアイデアは特にない。アイデアは暇から生まれるというのは概ね合っている気がする。いつも通り制御+非線形最適化をベースとした内容に留まりそう。恐らく博論までこうであろう。
今更過ぎるがロボティクスの中で博士でフォーカスするのが「制御」だったのはやや悪手だったように思う。面白いとは思うが、実務上は枯れた理論になりつつあるし、性能向上も重箱の隅で叩くようなレベルの物に留まる。かといって理論に偏重しすぎると数理的に複雑すぎてついていけそうにない。恐らくSLAMとかプランニングとかもう少しハイレイヤーのものにしても良かったかなと思う。まあ博論後マイナーチェンジできる程度のものなのでバイオを選んでしまったというレベルの致命傷ではない(失礼)。
一方論文を書きまくっていることでデータ分析は早くなったと思う。というか論文でこのデータの可視化は必要だからまとめて簡単に前もって出せるようにする。追加実験になっても同一形式ですぐ比較まで出せるようにする、というソフトウェア戦略のセンスが良くなりしょうもない出戻りが減った。
論文
一応8月にずっとやってたMPCの論文を出した、イタリアにいた頃からやってたのでサイド的プロジェクトとはいえ1年近くかかってしまっている。しかも査読も1年近くかかるらしい、クソすぎる。地味に初めての単独筆頭主著のジャーナル論文である。IEEE系の論文誌ではあるがそんなにリードタイムがあるなら査読は厳しいがリターンもでかいTransactionsのどれかにしてもよかったかもしれない。
前出した共同主著の論文もリバイスが帰ってきたが、これ正直ダメだろと思ってたが案外査読は優しめで追加実験は無かった。ただリバイス時間が3週間はタイトすぎ、しかも帰国と重なったので結局この期間はリバイス作業にほぼ時間が取られた。
そんでIROSはダメだった。理論と実装は大丈夫だが実験が甘すぎるとは思っていたが、エイヤで出したら満場一致でもっと実験しろというコメントでリジェクトとなった(残当)。今までリジェクトはほぼ新規性不足が原因だったので実験不足は珍しいケースだが、実験すればいいだけなので対応しやすい。だが再投稿先のICRAはIROSより少しレベルが上がるので本来IROSがアクセプトされたら追加してジャーナルにすることを考えてた内容も盛り込む事になった。まあこの程度の追加分でジャーナルとして出すには甘すぎるのでこれで良かったと思う。
Nature Communicationsの査読をした。いつも査読するRA-LやICRA、IROSに比べ論文のレベルは高いとは思うが、正直レビューのレベルはこんなもんかと思ってしまった。IEEE Transactions系の方が質の高いレビューが来ると思う。
学会
やたら学会に行った。以前は結構楽しかった気がするが、やや食傷気味になりつつあり学会に参加するということ自体を楽しめる感じでは全くなくなってしまった。しかも拠点が欧州になっていることもあり他の国に経費で行けるというモチベも前より弱まってしまった。
ただやはり行くべきか行くべきでないかという意味では行くべきだと思う。有意義感やためになっている感は所謂勉強会や専門的なサマースクールの方が高いが、ガチで出版するための最前線の情報収集には学会が一番効率が良いと思う。今の時代ネットで論文読めばそれでいいのはそうなのだが、やはり実際にデモを見たり当時者と話したり、ランダムに目に入ってくるものを肌感覚として吸収することに意味がある気がする。
ロボソフト
学会もうモチベねえわ的なことを書いたがこの学会は良かった。場所がEPFLのジュネーブだったというのも良い点だが、やはり専門性が絞られて参加人数も1000人未満程度のほうが必要なものを見切ることができるし、ネットワーキングもしやすい。自分の領域はいうほどソフトではないのだが、それでもこのくらいの規模のほうがいいな。参加費はキチガイみたいに高い。

ICRA
この位の格になるともはや採択され行くこと自体に意味があるが、規模はでかいわトピックまで把握しきれないわで結構無為な時間を過ごしてしまった。ただ前後の日程にあるワークショップは良い。各時ホットな専門性のみで集まりそこの最前線や話を聞けるのは面白い。
知り合いは増えてきたように思う。ロボソフトでもそうだったが毎回10人に届かないくらいは知り合いの参加者がいる。イタリア滞在時の周辺のネットワークが結構強く、意外と短期滞在も意味あるなと思った。ヨーロッパというかアカデミアは完全にコネ社会なので、今後の為にも持ちつ持たれつの関係になっておくことは大事である。
また、コミュニティが完全にヨーロッパ勢軸に切り替わってしまった感がある。というか元々の日本勢が来てなさすぎるのかもしれん。
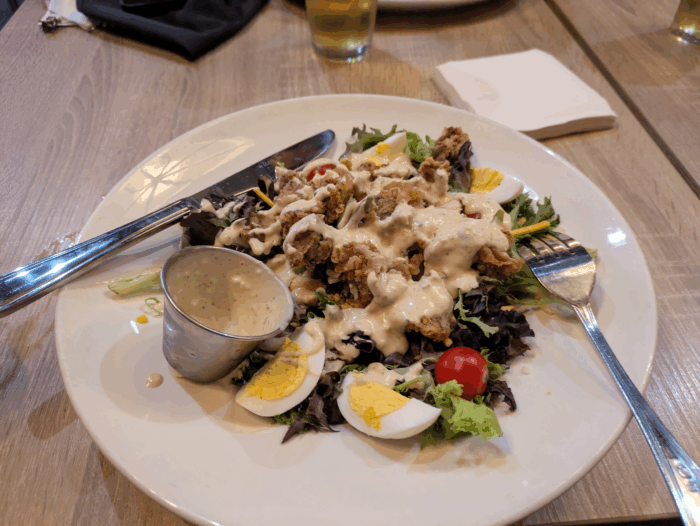
次ページは仕事とかゲームとか 月次のものは1Pにまとまるくらいの分量にしたい